柏餅は、日本の伝統的な和菓子であり、特に端午の節句には欠かせない存在です。
ふんわりと香る柏の葉に包まれたやわらかな餅と、なめらかなあんこの組み合わせは、世代を問わず愛され続けています。
しかし、いざ自宅で作ろうとすると「固くなってしまう」「うまく包めない」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初心者の方でも失敗せず、柔らかく美味しい柏餅を簡単に作れるように、材料選びから蒸し方のコツ、電子レンジを使った時短レシピまで、幅広く解説します。
また、和菓子屋のプロに学ぶポイントや家庭ならではの楽しみ方、子どもと一緒に作るアイデアも満載です。
保存方法や翌日以降も美味しく食べるための工夫、季節限定のアレンジレシピなど、知っておくと便利な情報も多数ご紹介。
伝統を大切にしながらも、現代のライフスタイルに合わせて無理なく楽しめる柏餅作りを、このガイドを通じてぜひ体験してみてください。
柔らかい柏餅のレシピ

材料の紹介と準備
- 上新粉:200g(国産米粉を使うと風味が良く、仕上がりが安定します)
- 白玉粉:50g(上新粉とのバランスで、もちもち感と柔らかさを出すのに重要です)
- 砂糖:大さじ2(お好みで増減可能。砂糖が生地の柔らかさにも影響します)
- 水:250ml(目安)(少しずつ加えながら、生地の硬さを調整してください)
- あんこ(こしあん/つぶあん):適量(市販でも可ですが、手作りだと風味が一段と良くなります)
- 柏の葉(塩漬け):必要枚数を水で戻す(塩分をしっかり抜くために、5〜10分ほど水に浸けておきましょう)
- 打ち粉用の片栗粉や上新粉:適量(成形の際、生地が手や道具にくっつくのを防ぎます)
- 包丁またはヘラ:生地の切り分けに使います
材料は一見シンプルですが、分量や順番、質にこだわることで、柏餅の仕上がりが大きく変わってきます。
準備段階でしっかりと計量し、手早く作業に移れるように整えておくのが成功のカギです。
上新粉と白玉粉の使い方
上新粉はもちもちした食感を生む主材料で、柏餅の基本となる部分を担っています。
精製された米を使っているためクセがなく、あんこの風味を引き立てる生地に仕上がります。
一方、白玉粉はもち米を原料とし、水に溶かすととても滑らかな粘り気を持つのが特徴です。
この白玉粉を上新粉に適量加えることで、生地がより柔らかく、しっとりとした食感になり、時間が経っても固くなりにくい仕上がりになります。
また、白玉粉の加える割合を変えることで、もちもち感や柔らかさの調整も可能です。
食感にこだわりたい方は、試行錯誤して自分好みのバランスを探すのも楽しみのひとつです。
あんこの選び方とおすすめ
こしあんは皮を取り除いた小豆で作られ、口当たりが非常になめらかで、小さなお子様から高齢の方まで食べやすいのが魅力です。
一方、つぶあんは小豆の皮が残っており、豆本来の風味や歯ごたえを楽しめるのが特徴です。
食感や味わいに違いがあるため、好みに応じて使い分けましょう。
また、あんこは自家製で作ると甘さや水分量を自由に調整でき、より自分好みの味が楽しめます。
自家製が難しい場合でも、市販の無添加・低糖タイプを選ぶと、健康にも配慮したおやつとして安心です。
保存料不使用のあんこを使うと、素材の味をより引き立ててくれるのでおすすめです。
昔ながらの柏餅の作り方

伝統的なレシピの概要
蒸し器を使い、生地を一度しっかりと蒸してから中にあんこを包み、再び蒸すことでしっとりとした食感と上品な仕上がりを実現します。
この伝統的な二段階の蒸し工程が、風味と食感の両方を引き立てる鍵となります。
手間はかかりますが、仕上がりは格別です。
必要な道具と蒸し器の選び方
家庭用の二段蒸し器や竹製のセイロがおすすめです。
セイロは蒸気が均一にまわりやすく、ふっくら仕上げることができます。
ステンレス製の蒸し器でも代用可能ですが、内側に布やクッキングシートを敷いて蒸し布の代わりにすると、生地のくっつきを防げます。
また、蓋にタオルやふきんを巻いて蒸気の水滴が落ちないようにするのも重要なポイントです。
小さな網台やシリコン製の蒸しマットがあると、さらに蒸しやすくなります。
手順ごとのポイント
- 白玉粉を水で丁寧に溶かしてから、上新粉と砂糖を加えて全体を均一になるまで混ぜます。粉のかたまりが残らないよう、泡立て器を使うと便利です。
- 混ぜた生地を蒸し器に入れ、10〜15分ほど蒸します。蒸した後は木べらなどで生地をよく練り、つき混ぜるようにして弾力を引き出します。この工程がもっちり感を出すコツです。
- 生地が熱いうちに適量をちぎって広げ、中にあんこを包みます。手早く包むことで形が崩れにくくなります。
- 包んだ餅は、あらかじめ戻しておいた柏の葉でくるみ、再度3〜5分ほど蒸します。これで葉の香りが移り、全体がしっとりと落ち着いた状態になります。
これらの手順を丁寧に行うことで、見た目にも美しく、柔らかさが長持ちする本格的な柏餅を家庭で楽しめます。
柏餅が固くならないコツ
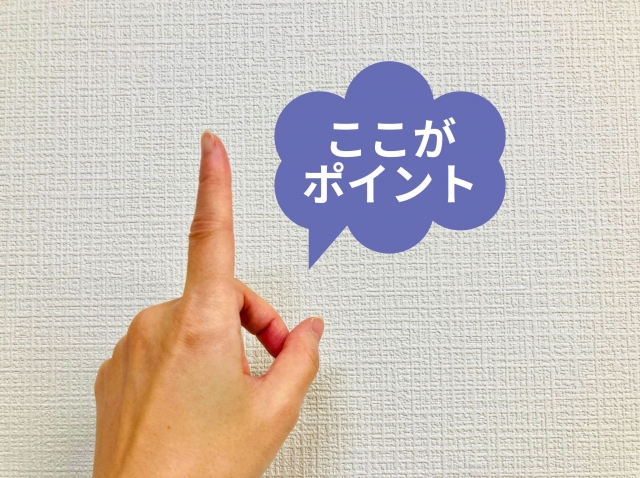
生地を柔らかくするための秘訣
白玉粉を加えること、水分量の調整、そして練る工程をしっかり行うことが柔らかい生地を保つための基本です。
白玉粉はもち米由来の強い粘りをもたらし、上新粉のみで作ったときよりも断然柔らかく仕上がります。
また、水分は一度にすべて加えず、少しずつ様子を見ながら加えることで、理想的な生地の柔らかさに調整しやすくなります。
練りは加熱後がポイントで、熱いうちに木べらや手でしっかりとこねることで、生地がなめらかになり、固くなりにくくなります。
この3つの要素を丁寧に行うことで、時間が経っても柔らかさを保てる柏餅に仕上がります。
加熱時間と温度の調整
加熱しすぎると生地の水分が飛んでしまい、硬さの原因になります。
蒸し時間は10分前後が適切ですが、生地の厚みや量によっては若干調整が必要です。
途中で蒸し器の蓋を開けると温度が下がるので、なるべく一定の蒸気温度を保つようにしましょう。
また、蓋に布巾を巻くことで蒸気が水滴になって生地に落ちるのを防ぎ、表面がベタつかず美しい仕上がりになります。
電子レンジ加熱の場合も同様で、ラップをふんわりかけて、蒸気を閉じ込めるようにすることでしっとりと仕上がります。
保存方法と翌日以降の工夫
できたての柏餅は粗熱が取れた段階で、1つずつラップに包んで乾燥を防ぎ、密閉容器に入れて保存します。
冷蔵庫に入れるとどうしても固くなってしまうため、保存は常温(ただし当日中)か、すぐに食べない場合は冷凍保存がおすすめです。
冷凍する際も1個ずつ包み、必要な分だけ取り出せるようにしておくと便利です。
解凍の際は電子レンジでラップに包んだまま軽く加熱すると、ふんわりとした食感が戻ります。
水を少しふりかけてから加熱するのも効果的です。
電子レンジで簡単柏餅

レンジを使った手軽な作り方
- 上新粉と白玉粉、砂糖をボウルに入れ、水を少しずつ加えながら泡立て器でダマにならないようによく混ぜます。全体がなめらかになるまで丁寧に混ぜてください。
- 混ぜ終わったら耐熱ボウルに移し、ふんわりとラップをかけて、電子レンジ(600W)でまず3分加熱します。このとき、加熱ムラを防ぐために途中で1度取り出し、全体をゴムベラでしっかり混ぜるとさらに良い仕上がりになります。
- 再度1〜1分半ほど追加で加熱し、もっちりとした粘りが出てきたら加熱完了です。取り出したら熱いうちに木べらなどで練り、生地がまとまり滑らかになるまでしっかり練ってください。
- 生地が扱いやすい温度まで冷めたら、手に打ち粉をつけて適量を取り、円形に伸ばしてあんこを包みます。
注意が必要な加熱ポイント
電子レンジは加熱ムラが出やすいため、途中で一度取り出して練り直すのがポイントです。
加熱しすぎると生地が硬くなるので、様子を見ながら加熱時間を調整しましょう。
また、加熱後すぐにラップを外すと乾燥の原因になるため、少し蒸らしてから成形するとより柔らかく仕上がります。
便利なラップの使い方
生地の成形にはラップが大活躍します。
広げたラップの上に生地を置いて押し広げることで、手にくっつかず衛生的に作業できます。
また、あんこを包む際にもラップを使えば、きれいな丸い形に整えやすくなり、包んだあとのラップごと保存することもできて便利です。
さらに、ラップは加熱時の水分保持にも役立ち、柔らかさを保つために欠かせないアイテムです。
人気の柏餅のバリエーション

こしあんとつぶあんの違い
こしあん:なめらかで上品な口当たりが特徴で、あんこの甘さや香りがしっかりと引き立ち、幅広い年齢層に好まれます。
口当たりが軽く、小さなお子さまや年配の方でも食べやすいのが魅力です。
つぶあん:豆感がしっかりと残り、小豆本来の風味と食感が楽しめるのが特徴です。
つぶつぶの食感が好きな方にはたまらない存在で、甘さ控えめにすると素材の味がより引き立ちます。
どちらも一長一短があり、季節やシーンに応じて使い分けるのがおすすめです。
季節限定の具材紹介
春には桜の香りが楽しめる桜あん、夏前にはよもぎ入りの爽やかな緑色の生地、秋には栗あんやさつまいもあん、冬には白あんと柚子を合わせた柚子あんなど、季節ごとに彩り豊かな具材が楽しめます。
抹茶あんは通年人気ですが、特に新茶の季節には香りが一段と引き立ちます。
季節限定の素材を取り入れることで、同じ柏餅でも違った表情が楽しめ、作る楽しみが広がります。
アレンジレシピの提案
和の要素を残しながら洋風にアレンジするのも楽しい方法です。
黒ごまあんは香ばしさとコクが特徴で、大人に人気の味わい。チョコあんは子どもにも人気があり、バレンタインやイベントにぴったりです。
きなこまぶしは、蒸しあがった餅にきなこをまぶすだけで簡単に風味豊かな和スイーツに早変わり。
他にも、抹茶パウダーを生地に練り込んだり、フルーツピューレを使った色付き生地など、アイデア次第でバリエーションは無限大です。
家族の好みに合わせて自由にアレンジしてみてください。
和菓子屋の柏餅に学ぶ

プロの技術と材料について
米粉の配合や蒸し加減の熟練の技が、柏餅の食感や味わいを大きく左右します。
上新粉と白玉粉の絶妙なバランスに加え、蒸し時間の微調整、温度管理など、和菓子職人の経験と感覚が生きる工程が詰まっています。
また、あんこの甘さや舌触りにもこだわりがあり、手作りならではの深い味わいを生み出します。
そして、使用する柏の葉にも違いがあります。
プロは香り高く肉厚で形の美しい柏の葉を厳選し、全体の印象を引き立てています。
実店舗での柏餅の購入方法
端午の節句が近づくと、多くの和菓子店で柏餅の予約販売が行われます。
人気店では早い段階で売り切れたり、予約分のみの販売となることもありますので、事前の情報収集が重要です。
地域に根差した老舗和菓子店では、毎年決まったレシピで丹念に作られた伝統の味を楽しむことができます。
試食をさせてくれる店舗もあるので、自分の好みに合った柏餅を見つけるのもひとつの楽しみです。
人気の和菓子屋リスト
- とらや(伝統のこしあんと美しい成形で全国的に有名)
- 鶴屋八幡(素材にこだわった風味豊かな逸品が揃う)
- 虎屋ういろ(名古屋の名店で、ういろとの融合を楽しめる)
- 菓匠花桔梗(季節感を取り入れたモダンな柏餅が魅力)
- 一幸庵(東京・小石川の名店。予約制の柏餅は評判が高い)
柏餅作りに役立つ道具

おすすめの蒸し器とその使い方
IH対応の多層構造蒸し器や、竹製のセイロが本格派に人気です。
多層構造の蒸し器は熱の伝導が均一で、短時間でふっくらと蒸し上げることができます。
一方で、竹製のセイロは通気性がよく、余分な水分を逃してくれるため、生地がベタつかず香りも引き立つのが魅力です。
和の雰囲気を演出できるため、見た目の美しさにもこだわる方におすすめです。
どちらも底に蒸し布やクッキングシートを敷いて使用することで、生地がくっつくのを防ぐことができます。
蒸し器のサイズは家庭用として直径20〜24cm程度のものが扱いやすく、人数に応じて複数段使えるタイプを選ぶと効率的です。
ボウルや計量器の選び方
耐熱ボウルは電子レンジでも使用できるため、電子レンジ加熱で柏餅を作る際には非常に便利です。
透明なガラス製のボウルを使うと、中の状態が確認しやすく、混ぜ具合のチェックにも役立ちます。
ステンレス製のボウルは軽くて丈夫なので、生地を練るときや蒸し器への移し替えにも適しています。
デジタル計量器は1g単位で計れるものがおすすめで、粉の分量を正確に量ることで失敗を防ぐことができます。
複数の材料を順番に加えるレシピには、風袋引き(ゼロリセット)機能があると便利です。
合わせて、小さめの計量スプーンや注ぎ口付きの計量カップも用意しておくと、作業がよりスムーズになります。
富澤商店の利用について
和菓子材料の品揃えが豊富で、上新粉や白玉粉、こだわりのあんこなど多彩な商品が揃っています。
店舗では材料だけでなく、蒸し器やセイロ、計量器や耐熱ボウルなど道具類も豊富に取り扱っており、初心者が一から揃える際にも安心です。
また、スタッフによる商品説明やレシピの紹介もあり、分からないことを気軽に相談できるのも魅力の一つです。
オンラインショップも充実しており、全国どこでも手軽に必要なアイテムが手に入ります。
初心者向けのスターターセットや季節限定の和菓子キットも販売されており、自宅での和菓子作りがさらに楽しく、身近なものになります。
家庭での柏餅作りの楽しさ

子どもと一緒に作れるレシピ
あんこを包む作業は子どもでも簡単で、粘土遊びのような感覚で楽しめます。
生地を伸ばしてあんこを包むという一連の作業は、子どもの手先の発達にも良く、親子で一緒に行えば自然と会話も弾みます。
普段はなかなか一緒に料理をしない家庭でも、特別なイベントとして楽しい時間を過ごせるきっかけになります。
子どもたちは自分で作った柏餅に特別な愛着を持ち、食べる楽しみも倍増します。
また、完成した柏餅に名前を書いたりシールを貼ったりすることで、オリジナル作品としての達成感も味わえます。
家族で楽しむ柏餅パーティ
味の違う柏餅を数種類作って食べ比べるのも楽しいアクティビティです。
こしあん、つぶあんだけでなく、抹茶あん、桜あん、さらにはチョコあんやフルーツあんなど、バリエーション豊富に用意して、自分の好みに合った味を見つけるのもイベントの醍醐味です。
見た目もカラフルに仕上がるので、SNS映えする写真を撮ったり、家族や友人とその場で感想をシェアしたりと盛り上がります。
季節の草花を飾って和の雰囲気を演出するのもおすすめです。
日常のご褒美としての柏餅
柏餅は、季節の風物詩としてだけでなく、日常生活の中でちょっとしたご褒美として取り入れるのにも最適なお菓子です。
忙しい毎日の中で、自分へのねぎらいの時間として、手作りの柏餅を味わうことで心がホッと和みます。
手作りだからこそ甘さの加減や中身のバリエーションも自由自在で、体調や気分に合わせて調整できます。
また、和菓子は洋菓子に比べて脂質が少なく、ヘルシーなおやつとしても人気があり、美容や健康を意識する方にもおすすめです。
作り方を見直す

失敗しない生地のこね方
耳たぶの柔らかさを目安にしっかり練ることで、滑らかで割れにくい生地に仕上がります。
生地をこねる際には、力強く押しつぶすように練り込むことで、空気が抜けてきめ細かくなり、粘りと弾力が出てきます。
生地の状態を手のひらで確認しながら、数分かけてじっくりと練りましょう。
表面がつややかになり、手にほとんどくっつかなくなるまでしっかりこねるのが理想的です。
また、練る際に水分が足りないと感じた場合は、ごく少量のぬるま湯を加えると扱いやすくなります。
このこね作業が甘いと蒸した後にひび割れや硬さが出ることがあるため、丁寧に時間をかけることが、美しく美味しい柏餅作りの秘訣です。
蒸し時間の目安と調整
10〜15分を目安に、生地の弾力を確認しながら調整しますが、生地の厚みや使用する蒸し器の性能によっては加熱時間を微調整する必要があります。
たとえば、生地が厚めの場合は内部までしっかり火を通すために18分ほど蒸すこともあります。
一方で、生地が薄めであれば12分程度で十分な場合もあります。
蒸している途中に一度取り出して、指で軽く押して弾力を確認すると、適切な状態かどうか判断しやすくなります。
表面に光沢が出て、指で押してもすぐに戻るような弾力が出ていれば、ちょうど良い蒸し加減です。
また、蒸しすぎると表面が乾燥し、ひび割れの原因になるので、時間と火加減をこまめに確認することが成功のポイントです。
よくある質問と答え
Q: 柏の葉は食べられる?
A: 食べることは可能ですが、柏の葉は本来、風味を生地に移すために使われており、香り付けが目的です。
葉自体はしっかりしていて噛み切りにくいため、一般的には取り外してから中の餅をいただきます。
ただし、葉の香りを感じながら味わうことで、より一層風情が増すため、包んだままいただくのも楽しみ方のひとつです。
また、柏の葉には抗菌作用があるとされ、保存性を高める役割も果たしています。
Q: 冷蔵保存したら固くなった!
A: 冷蔵保存は水分が奪われやすく、生地が硬くなる原因になります。
できるだけ当日中に食べきるのが理想ですが、保存が必要な場合は、1個ずつしっかりラップで包み、密閉容器に入れて冷凍保存するのがベストです。
冷凍した柏餅は、食べる際に電子レンジでラップごと加熱すれば、ふんわりとした柔らかさが戻ります。
加熱する前に少量の水を表面に振っておくと、さらにしっとりと仕上がります。
自然解凍でも食べられますが、よりふわっとした食感を求めるなら加熱がおすすめです。
まとめ
柏餅は、日本の伝統行事に欠かせない和菓子でありながら、家庭でも手軽に楽しめるスイーツです。
本記事では、上新粉と白玉粉の使い分け、生地が固くならないコツ、蒸し器・電子レンジの両方に対応した調理法、さらには保存方法やアレンジレシピに至るまで、幅広く丁寧に解説してきました。
特に重要なのは、「生地の柔らかさを保つポイント」を押さえることと、「楽しみながら作る姿勢」です。
子どもと一緒に作ったり、季節の素材を取り入れたりすることで、柏餅作りは単なる料理を超えた楽しい家族イベントになります。
伝統の味を守りながらも、自分なりのアレンジを加えたり、プロの技術に学んだりすることで、毎年の端午の節句がもっと待ち遠しくなるはずです。
ぜひ今回のガイドを参考に、あなたの家庭でもふんわり香る柏の葉に包まれた、やさしい味わいの柏餅を楽しんでみてください。

