保育士を目指す方にとって、保育士試験の「合格率」は最も気になる情報のひとつではないでしょうか。
保育の現場では深刻な人材不足が続いており、その一方で国家資格である保育士資格を取得するには、高いハードルを越える必要があります。
本記事では、2025年に向けた保育士試験の最新合格率を中心に、試験制度の概要や過去の推移、地域差、そして合格者の傾向など、あらゆる視点から「保育士試験の実態」を徹底的に解説します。
さらに、合格に必要な勉強時間や対策方法、信頼できる通信講座や実技試験の準備法なども紹介。
これから受験を考えている方はもちろん、再チャレンジを目指す方にとっても、具体的なヒントが満載です。
ぜひ最後までご覧いただき、確実に合格をつかむための第一歩を踏み出しましょう。
保育士試験の合格率とは?

保育士試験の概要を理解する
保育士試験は、厚生労働省が所管する国家資格試験であり、保育所、認定こども園、児童福祉施設などで働く際に必要とされる非常に重要な資格です。
子どもたちの健全な発達や生活支援に関わる専門職として、保育士の役割は年々注目を集めており、そのニーズも高まっています。
試験は大きく筆記試験と実技試験に分かれており、まず筆記試験で全8科目に合格することが求められます。
この筆記試験に合格した受験者のみが、次のステップである実技試験へと進むことができます。
なお、受験資格については学歴や実務経験などによって異なり、たとえば大学や短期大学、専門学校での保育関連課程を修了した人、あるいは一定の実務経験を有する人などが対象となります。
そのため、誰でもすぐに受けられるわけではなく、受験前に自分の条件を確認することが重要です。
合格率の重要性と影響
保育士試験の合格率は、単なる数値ではなく、試験の難易度や出題傾向、さらには受験者の全体的な学習準備度を反映する極めて大切な指標です。
この合格率は、受験を検討している人たちのモチベーションに大きく影響を与えます。
たとえば、合格率が高く報告される年度は、受験への心理的ハードルが下がり、より多くの人が挑戦しようとする傾向があります。
一方で、合格率が著しく低い場合は、受験を躊躇する人が増えたり、試験対策に対する不安が大きくなることもあります。
合格率はまた、教育現場や保育業界全体の人材供給にも直結する要素であり、保育士不足の状況を改善する上でも注目されるべきデータです。
令和5年の合格率の実態
令和5年(2023年度)に実施された保育士試験の合格率は、最新の公式発表によると、筆記試験での合格率が約25%と、前年と比較してやや上昇傾向にありました。
これは、過去問題の傾向を踏まえた対策が広く普及していることや、受験者の意識の高まりが要因と考えられています。
一方、実技試験に関しては、おおよそ70%前後という比較的高い合格率を維持しており、受験者の準備の質が安定してきたことがうかがえます。
最終的に、筆記と実技の両方に合格して資格を取得できた人の割合、つまりトータルの合格率はおよそ15〜18%程度にとどまり、依然として難易度の高い試験であることに変わりありません。
こうした数値は、計画的な学習と対策の必要性を改めて示していると言えるでしょう。
保育士試験の合格率の推移
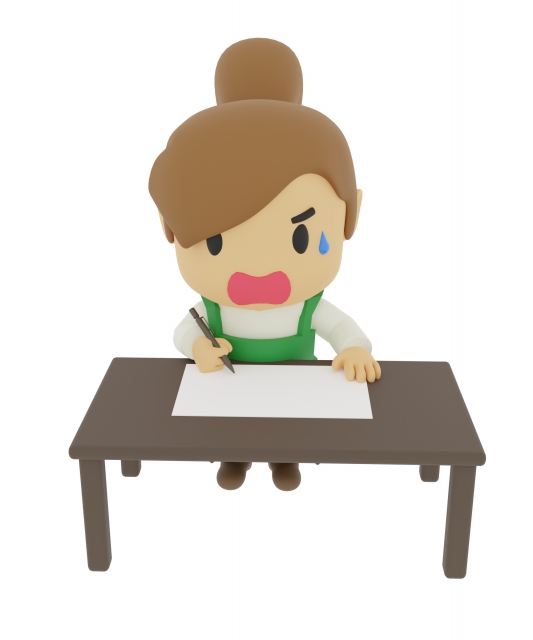
過去5年の合格率推移を分析
過去5年間の保育士試験の合格率を振り返ると、年度ごとに多少のばらつきがあるものの、全体的には15〜20%程度の範囲で安定的に推移していることがわかります。
特に筆記試験については一貫して難易度が高く、合格率も20%前後にとどまっており、受験者にとっては最初の大きな関門となっています。
一方、実技試験の合格率は相対的に高く、60〜70%程度で推移しています。
これは、筆記試験に合格した時点である程度の基礎知識と意欲を持った受験者が絞り込まれているためと考えられます。
近年では、受験者数の増減や出題傾向の変化により若干の上下はあるものの、大きく変動することはなく、一定の難易度が維持されています。
合格率が高い年度とその要因
過去には合格率が例年よりも高くなった年度もあり、その背景にはいくつかの要因が存在します。
たとえば、出題傾向が過去問とよく似ており、受験者が十分に対策を講じやすかった年や、保育士不足が深刻化していた時期には、採用促進の観点から制度面の柔軟化が図られたこともあります。
また、感染症流行下においては試験環境の配慮として内容の一部が変更され、比較的取り組みやすい形式が採用された年もありました。
その結果、特定の年では合格率が一時的に上昇する現象が見られました。
合格率の地域差について
保育士試験の合格率には、都道府県ごとに明確な地域差が存在しています。
都市部では受験者数が多く、競争が激しくなるため、平均して合格率はやや低めに出る傾向があります。
これに対し、地方では受験者数が限られていることや、地元に根ざした学習サポートが充実しているケースもあることから、合格率が比較的高くなることがあります。
さらに、自治体によっては独自に試験対策講座を開催している地域もあり、その有無が合格率に影響を与えている場合もあります。
こうした地域差は、学習環境や受験者の生活背景、支援制度の充実度など、さまざまな要因が複雑に絡み合って形成されていると言えるでしょう。
保育士試験の合格に必要な要素

受験資格と試験科目の概要
受験資格は、保育士試験を受験するにあたり最も基本的な要件となります。
基本的には、専門学校や短期大学、四年制大学などで保育士養成課程を修了していることが条件です。
これらの課程では、子どもの発達や保育実習など、現場に直結する知識と経験を学ぶことができます。
また、福祉系・教育系の学部を卒業している場合や、一定年数以上の保育業務経験を有している場合にも、受験資格を得ることができます。
近年では、社会人経験者や子育て経験を持つ人など、多様な背景を持つ受験者が増えており、それに伴って受験資格の柔軟化も進んでいます。
試験科目は全部で8科目あり、具体的には保育原理、教育原理、社会的養護、児童家庭福祉、社会福祉、子どもの保健、子どもの食と栄養、そして保育の心理学が含まれます。
それぞれの科目で合格基準をクリアする必要があるため、バランスよく学習を進めることが求められます。
筆記試験と実技試験の違いと難易度
筆記試験は主にマークシート方式で実施され、幅広い知識を問われるため、学習範囲が非常に広いのが特徴です。
1科目ごとの内容も専門的で、過去問の出題傾向を把握しながら、効率的な暗記と理解の両立が必要です。
一方の実技試験では、「音楽表現に関する技術」「言語表現に関する技術」「造形表現に関する技術」の3つの分野から2つを選んで受験します。
実技試験では実際に演奏したり、絵を描いたり、子どもに読み聞かせを行うといった形式で、自身の表現力や対応力が問われます。
さらに、本番での緊張にどう対処するかも大きなポイントとなります。
筆記試験よりも短時間で終了する実技試験ですが、評価基準が明確でない部分もあるため、十分な準備が不可欠です。
保育士試験に向けた効果的な勉強法
効果的な勉強法としては、まず過去問題集を繰り返し解くことが基本です。
出題傾向を理解し、頻出テーマを押さえることで得点力が安定します。
また、単なる暗記にとどまらず、各テーマの背景や関連知識まで深く理解することが、応用問題に対応する鍵となります。
さらに、勉強スケジュールの管理も重要です。
日々の学習時間を確保し、無理のない範囲で継続することが合格への近道です。
特に社会人受験者は、仕事や家庭との両立が求められるため、隙間時間を活用する工夫も欠かせません。
動画教材や音声講座などを活用し、通勤時間や家事の合間に知識をインプットするのも効果的です。
合格者に共通する特徴
保育士試験に合格する人々にはいくつかの共通点があります。
まず挙げられるのが「継続的な学習習慣」です。
短期的な詰め込みではなく、長期間にわたってコツコツと積み重ねていく姿勢が成功の鍵です。
また、「時間管理能力」に優れており、試験までの期間を逆算して学習計画を立てることができる人が多く見られます。
さらに、実技対策についても「本番を想定した実践練習」を重視している傾向があります。
模擬試験やグループ練習などを通じて、人前でのパフォーマンスに慣れることで、本番でも落ち着いて対応する力が養われます。
最後に、保育士として働くことへの強い「動機」と「目標意識」を持っていることも重要です。
子どもと関わる仕事への情熱が、日々の学習や試験当日の集中力に大きな影響を与えると考えられます。
一発合格を目指すための対策
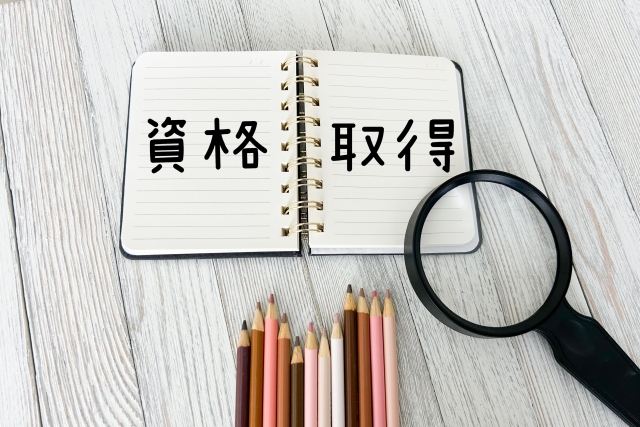
過去問を活用した勉強法
過去問を繰り返し解くことで出題傾向が明確になり、試験に対する戦略が立てやすくなります。
特に頻出テーマやよく出題される形式を把握しておくことは、得点力を安定させるうえで非常に効果的です。
また、間違えた問題をそのままにせず、なぜ間違ったのかを分析することが重要です。
解説を丁寧に読み込み、背景知識や関連分野の理解を深めることで、同様の問題が出題された際にも自信を持って解答できるようになります。
さらに、正解した問題についても「なぜそれが正解なのか」を確認する習慣を持つことで、表面的な暗記にとどまらない応用力が身につきます。
役立つ通信講座や専門学校の紹介
通信講座では、ユーキャンやキャリカレのような実績のある教育機関が提供するプログラムが人気です。
これらの講座では、最新の出題傾向に対応したテキストや問題集、スマートフォンでも視聴可能な動画講義、添削指導付きの課題などが含まれており、初心者からでも安心して学習を進めることができます。
また、専門学校では東京福祉専門学校や大原学園などが代表的で、対面授業や実技指導に力を入れているため、実際の保育現場を意識した指導を受けられる点が強みです。
特に実技対策においては、現役の保育士や音楽・美術の専門家が直接指導するカリキュラムが組まれていることも多く、より実践的なスキルを身につけることができます。
実技試験対策におすすめの練習方法
実技試験においては、「音楽」「言語」「造形」の3分野から2つを選択する必要があり、それぞれに応じた対策が欠かせません。
ピアノ練習では、保育園でよく使われる童謡を弾き語りできるようにするのが基本です。
自宅にキーボードがあれば、短時間でも毎日練習を継続することが上達への近道です。
絵の描き方については、課題に沿って時間内に作品を完成させる力を養うことが求められます。
色鉛筆やクレヨンなどの基本的な画材を使い、テーマ性や子どもらしさを意識した表現練習が効果的です。
読み聞かせなどの言語表現では、発音の明瞭さや間の取り方、子どもが引き込まれるような語り口を意識して練習することがポイントです。
動画教材や模擬試験の活用はもちろん、実際に家族や友人に見てもらって緊張感を体験することも、本番に強くなるための重要なステップです。
保育士試験の受験スタイルとスケジュール
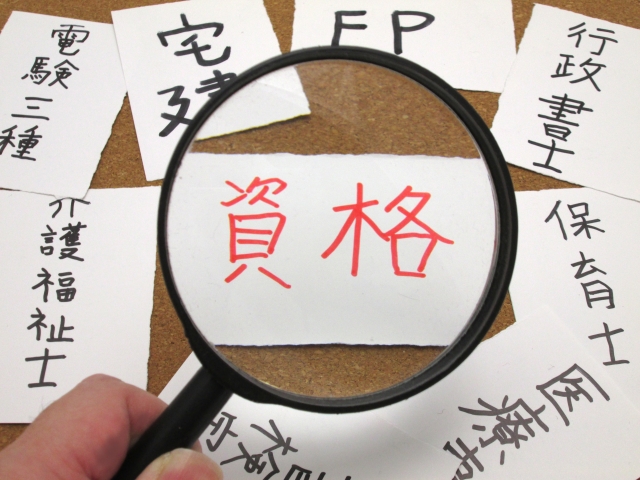
前期と後期の試験の違い
保育士試験は年に2回、前期(4月実施)と後期(10月実施)に分かれて行われます。
どちらの回を受験するかによって学習のスケジュールや準備期間が異なってくるため、まずは自身の生活リズムやスケジュール、家庭や仕事との両立可能性をよく検討することが大切です。
前期試験を選べば、年明け早々から学習に集中する必要があり、寒さや年始の慌ただしさの中での準備になります。
一方、後期試験は夏以降に本格的な勉強を開始するスタイルになるため、比較的余裕をもって対策できるというメリットがあります。
とはいえ、どちらの試験も難易度や出題内容に大きな違いはありません。
重要なのは、自分にとって無理のないスケジュールを組み、継続して勉強を進めることです。
特に社会人や育児中の方にとっては、試験の時期選びが学習効率を左右するため、前もって計画を立てることが合格への第一歩となります。
受験日時と試験準備のタイムライン
保育士試験の申込から実際の受験までは約3か月間の準備期間が設けられています。
前期試験の申込受付は例年1月上旬から始まり、後期試験は7月初旬にスタートします。
筆記試験は通常、前期は4月下旬ごろ、後期は10月中旬から下旬にかけて実施され、結果通知までは数週間を要します。
筆記試験に合格した場合、次は実技試験に進むことになりますが、この実技試験は筆記試験から約2か月後に設定されており、例年であれば前期は7月上旬、後期は12月上旬に実施されます。
この期間を活かして、十分に実技対策の時間を確保できるよう計画することが求められます。
また、試験対策においては、筆記と実技を分けて段階的に取り組むことが重要で、特に筆記試験に集中する期間には基礎知識の習得に注力し、合格発表後から実技の練習にシフトするスタイルが多くの合格者に支持されています。
早期にスケジュールを立て、毎月・毎週・毎日の目標を定めて学習を進めることで、効率よく準備を進められるでしょう。
合格後のキャリアと求人情報
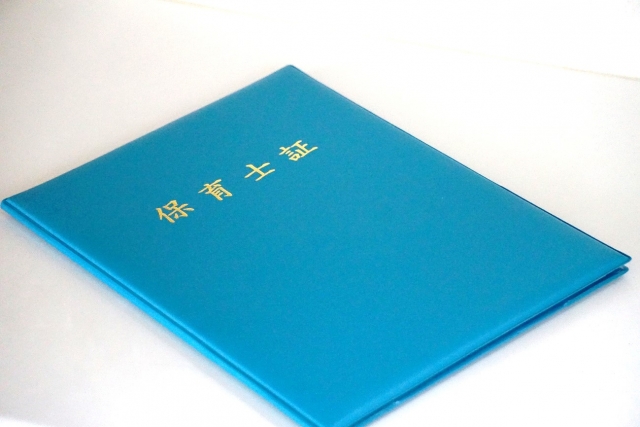
保育士の仕事の実態とやりがい
保育士は、子どもの成長を身近で支えられるという非常に意義のある職業であり、多くのやりがいを感じられる仕事です。
日々の保育活動を通じて子どもの笑顔や成長を見守ることができるのは、この職業ならではの魅力です。
また、保護者との信頼関係を築き、家庭との連携を図るなど、社会的役割も大きく、地域の子育て支援の一端を担う存在でもあります。
一方で、長時間労働や人間関係、給与面での課題など、職場環境の改善が求められるケースも多くあります。
最近では働き方改革の影響を受けて、労働条件の見直しや保育士の処遇改善に取り組む自治体や施設も増えてきています。
実際の現場を事前に見学することで、職場の雰囲気や業務内容を把握し、自分に合った環境を選ぶことが重要です。
合格後の転職に向けたポイント
保育士試験に合格した後は、就職活動をスムーズに進めるために早めの準備が鍵になります。
まずは転職サイトや求人情報誌、自治体の保育人材センター、ハローワークなど複数の手段を活用して情報収集を行いましょう。
特に未経験から保育士を目指す方や、子育てなどでブランクのある方には、「未経験歓迎」「ブランク可」などの条件が記載された求人を選ぶとスムーズです。
近年では、企業内保育所や小規模保育園など、多様な働き方が可能な施設も増えており、勤務時間や待遇面の選択肢が広がっています。
面接時には、自分の保育観や志望動機をしっかり伝えることが大切であり、実習やボランティアの経験をアピールするのも効果的です。
就職後のミスマッチを防ぐためにも、職場見学や現場スタッフとの面談の機会を活用して、自分に合った職場を見極めることが成功のカギとなります。
保育士試験に関するよくある質問

保育士試験にかかる費用はどのくらい?
受験料は令和6年度時点で12,950円と定められていますが、これに加えて必要となる学習費用も無視できません。
たとえば市販の参考書や問題集を揃えるだけでも5,000円〜10,000円程度の費用がかかり、さらに効率的に学習を進めたい方は通信講座や対面講座などの教育サービスを利用することが多く、これらは1〜3万円程度が相場です。
自習用のノートや文具、オンライン模試の受講費なども含めると、トータルでかかる費用は3万円〜5万円、場合によってはそれ以上に上ることもあります。
特に初めて受験する方や独学に不安を感じる方は、教材にしっかり投資することで合格の可能性を高めることができるため、費用をかけるべきポイントを見極めることが重要です。
合格率を上げるための勉強時間の目安
筆記試験の対策としては、200〜300時間を目安に勉強時間を確保する必要があると言われています。
これは、1日1〜2時間の学習を3〜6か月間続ける計算になります。
特に働きながら勉強する人にとっては、休日や早朝、通勤時間などを有効活用する工夫が求められます。
科目数が8つと多いため、日ごとにテーマを分けて効率よく復習するスタイルが効果的です。
実技試験に向けた準備も重要で、50〜100時間程度を見込んでおくと安心です。
音楽表現や造形表現に不慣れな方は、より多くの時間を割く必要があります。
いずれも「毎日の積み重ね」が結果に直結するため、学習記録をつけるなどしてモチベーションを維持する工夫も大切です。
試験日当日の注意点と服装
試験当日は、受験票、写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を必ず持参しましょう。
万が一忘れてしまうと、試験を受けることができない可能性もあるため、前日までに持ち物チェックリストを作成し、事前に準備しておくことをおすすめします。
服装は原則として自由ですが、試験監督や周囲に不快感を与えない、清潔感のあるカジュアルスタイルが無難です。
筆記試験では長時間座っていることが多いため、疲れにくい服装と靴選びもポイントです。
実技試験では、ピアノ演奏や身体表現を行うこともあるため、動きやすさと見た目の印象を両立させた服装が望まれます。
また、冬季の実施の場合は防寒対策も忘れずに。
試験当日は緊張することが多いため、時間に余裕を持って会場に到着し、心にゆとりを持って臨むことが大切です。
まとめ
保育士試験は、子どもたちの成長を支える専門職として欠かせない国家資格です。
本記事では、2025年の最新情報をもとに、合格率の実態や過去の推移、地域差、そして合格するために必要な勉強法や試験対策を詳しくご紹介しました。筆記試験と実技試験の両方を突破するには、計画的な学習と十分な準備が不可欠です。
また、合格後のキャリアの広がりや保育士としてのやりがいにも触れ、試験を超えた未来のビジョンも描けたのではないでしょうか。
これから保育士試験に挑戦される方は、ぜひ本記事の内容を参考にしながら、自分に合った学習スタイルを見つけ、焦らず一歩ずつ着実に準備を進めてください。
未来の保育の現場で、あなたの力が子どもたちの笑顔を支える日を心から応援しています。

