「*」や「※」といった記号を見かけたことはありませんか?
ビジネス文書や案内文、Webサイトの注釈など、さまざまな場面で使われているこれらの記号は、それぞれ意味や用途が異なります。
特に「アスタリスク(*)」と「米印(※)」は混同されやすい一方で、正しく使い分けることで文章のわかりやすさや信頼性がぐんと向上します。
本記事では、アスタリスクと米印の違いを徹底的に解説し、それぞれの意味、使い方、注意点から実際の使用例に至るまで詳しくご紹介します。
記号の使い方に迷った経験がある方、文書作成の質を高めたい方はぜひ最後までご覧ください。
アスタリスクと米印の基本知識
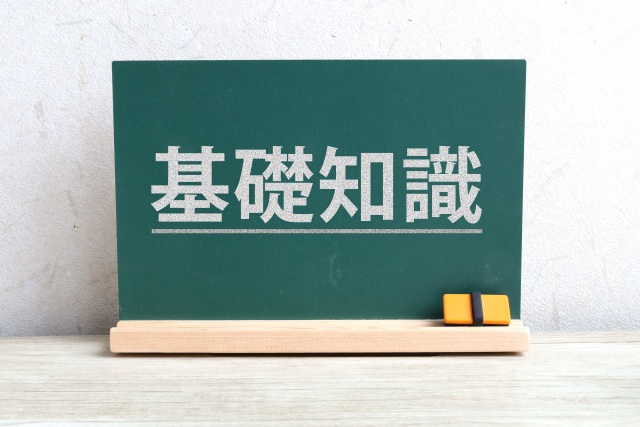
アスタリスクとは?その意味と正式名称
アスタリスク(*)は、「星印」や「星型記号」とも呼ばれる記号で、正式には「アステリスク(asterisk)」といいます。
語源はギリシャ語の「asteriskos(小さな星)」に由来し、その見た目からも「小さな星」のように見えるため、この名が付けられました。
アスタリスクは、文書やテキストにおいて注釈や補足情報を明示する際に非常に役立ちます。
また、コンピュータプログラミングの世界でも広く利用され、演算子としての役割(掛け算やポインタの表現など)や、ワイルドカード(任意の文字列の代替)としても用いられることがあります。
加えて、数学では積を示すために使われるほか、強調や省略表現にも活用されるなど、その用途は非常に多様です。
米印とは?使い方と由来
米印(※)は、日本独自に発展した記号であり、「こめじるし」と読みます。
その名の通り、「米」という漢字を図案化した形状から生まれたとされ、日本語文書の中で補足情報や注釈、特記事項を明確に示す目的で使用されます。
特にフォーマルな文書や紙媒体の資料において頻繁に見られ、視認性が高く、注意喚起の機能も果たします。
起源については諸説ありますが、戦前の日本の印刷技術の中で自然と定着した記号と考えられており、現代においてもその機能性から根強く使われ続けています。
特に公式文書や案内状、契約書などの中で、誤解のない明確な情報伝達を求められる場面に適しています。
アスタリスクと米印の違いを知ろう
アスタリスクは世界的に通用する国際的な記号であり、さまざまな用途で使用される一方で、米印は日本語に特化した記号として、より限定的な文脈で用いられます。
アスタリスクはデジタル文書やプログラミング、国際的なレポートやプレゼン資料などでも見られますが、米印は主に日本国内向けの文書に使われ、視覚的にも少し重みのある印象を与えます。
また、アスタリスクはシンプルな形状のため目立ちにくい一方、米印は複雑な線で構成されており視認性が高く、強調効果があるのが特徴です。
このように、それぞれの記号には適した文脈があり、場面や用途に応じて適切に使い分けることが重要です。
アスタリスクの使い方

ビジネス文書におけるアスタリスクの役割
アスタリスクは、文中で補足説明や注意書きなどを加える際に便利な記号です。
そのシンプルな形状と視認性の高さから、多くの文書において注釈を示すスタンダードな手段として用いられています。
特にビジネス文書やプレゼン資料、教育関係の配布資料などにおいて、本文の流れを邪魔することなく、必要な情報を補足的に伝えることができます。
また、脚注を設ける際にもよく使われ、文章内の視覚的な目印として非常に有効です。
複数の注釈がある場合には、アスタリスク(*)に続き、**(二重アスタリスク)、†(ダガー)、‡(ダブルダガー)など、段階的に記号を変える方法が一般的です。
これにより、注釈ごとの区別が明確になり、読者の理解を助けることができます。
一般的な文章でのアスタリスクの読み方と打ち方
読み方は「あすたりすく」または「ほしじるし」とされ、日本語文書でも柔軟に使われています。
入力方法は非常に簡単で、パソコンのキーボードではShiftキーを押しながら「8」のキーを押すことでアスタリスクが入力されます。
スマートフォンやタブレットの場合でも、記号入力モードに切り替えることで容易に入力が可能です。
また、ワープロソフトやHTMLエディタなどでは特殊記号としての挿入機能も備わっており、記述の際に迷うことはほとんどありません。
アスタリスク記号の使用例と注意点
使用例:
- 価格:3,000円(税込)
- 補足:本商品はオンライン限定販売です。
- 注意書き:*本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
アスタリスクは簡単に強調や注釈を加えられるため便利な一方で、使用頻度が高すぎると文章の視認性が損なわれ、読み手にストレスを与えることもあります。
特に一文の中に複数のアスタリスクを使用すると、文意が曖昧になったり、注釈の内容が混同される恐れがあるため、必要最低限にとどめ、明確な区別と使い方を意識することが大切です。
また、フォントや媒体によってはアスタリスクが小さく表示されることもあるため、視認性を確保する工夫も求められます。
米印の使い方
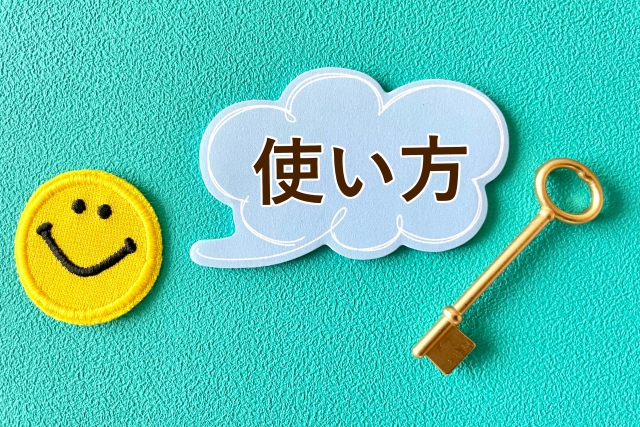
ビジネスシーンでの米印の重要性
米印は、文中で特に重要な注意点や例外事項を明確に伝えるために非常に有効な記号であり、日本語文書における注釈の定番です。
契約書では法的な条件の例外を示すために使用され、案内文では追加の説明や注意事項を明記するために重宝されます。
また、報告書などの公式な文書では、情報の正確性や補足説明を補う目的で用いられ、読者の理解を助ける役割を果たします。
米印は視認性が高く、文章の中で注意を引きやすいため、読み手に特定の情報を強く印象づける効果もあります。
米印を使う際のルールと読み方
読み方は「こめじるし」といい、日本語独特の文化的背景を持つ記号です。
使い方としては、文章中に※を付けて、文末あるいは欄外にその補足内容を明記するのが一般的です。
文中に複数の注釈を入れる場合は、※、※※、※※※と繰り返すか、別の記号(†、‡など)と併用するケースもあります。
また、米印はフォントや使用媒体によって表示の仕方に若干の違いがあるため、印刷物やPDFなどで使用する際は、実際の表示結果を確認しておくことが推奨されます。
特に細かいフォントや解像度の低い出力環境では、米印の視認性が損なわれる可能性があるため注意が必要です。
米印の打ち方:5本と6本の違い
米印には線の数によるバリエーションがあり、一般的には5本線で構成された※が最も多く使用されています。
この5本線の形状は、多くのワープロソフトや日本語入力システムに標準搭載されているため、汎用性が高く、文書作成時にもスムーズに使用できます。
まれに6本線で描かれた米印が使われることもありますが、これはフォントデザインや特殊な印刷レイアウトによる違いであり、用途や意味において大きな差異はありません。
ただし、読み手によっては違和感を覚える可能性があるため、統一感を重視する文書においては、あらかじめ使用する米印のデザインを統一することが望ましいでしょう。
アスタリスクと米印の使い分け

適切な場面でのアスタリスクと米印の使い方
- 国際的・デジタル文書:アスタリスクが適しています。
たとえば、国際的な企業の契約書や多言語対応が求められるWebサイト、さらにはソフトウェアやアプリケーションのUI上で補足情報を示す際にも、アスタリスクは非常に有効です。
理由は、アスタリスクが英語圏を含む多くの文化で広く理解されており、かつ記号としての視認性や互換性が高いためです。
- 日本語の印刷文書:米印の方が自然です。
特に公的文書、学校の通知、パンフレット、紙の広告チラシなど、日本語のみで構成された印刷物では米印が使われる傾向が強く、読み手にとっても馴染みが深いため、注釈や注意書きの意図がより明確に伝わります。
アスタリスク vs 米印:どちらを選ぶべきか
文書の種類、対象読者、使用目的、そして文書のフォーマルさを慎重に考慮して記号を選ぶことが重要です。
アスタリスクは国際的な認知度が高く、IT関連や英文のドキュメントにおいて広く使用されているため、英語を含むビジネスレター、テクニカルドキュメント、海外向けのマーケティング資料などでは非常に自然で信頼感を与える選択肢です。
一方、日本語を主とする案内文、公共文書、社内通知、学校配布資料などでは、視認性が高く、丁寧でフォーマルな印象を与える米印がより適しており、読者にとってもなじみやすいという利点があります。
また、印刷かWebかといった媒体の違いや、注釈の情報量なども選定の判断材料に加えると、より的確に使い分けができます。
ケーススタディ:文書作成時の具体例
- 契約書:「支払いは翌月末までに行ってください※延滞の場合は利息が発生します。
※また、支払いの遅延が繰り返された場合は契約解除の対象となることがあります」
- プロダクト説明:「この商品は一部地域を除き送料無料です。
*ただし、沖縄・離島などの一部地域では別途送料が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください」
まとめとQ&A

アスタリスクと米印に関するよくある質問
Q: Q: 両方使ってもいい?
A: 可能ではありますが、読者にとっての視認性や文意の明確さを保つためには、同一文書内での記号の混在はなるべく避けた方が良いとされています。
特に長文や複雑な構成を持つ文書では、使用記号が統一されていることで注釈の意図が明確になり、読み手が情報を正しく受け取りやすくなります。
用途やシーンによって使い分けるのは効果的ですが、一つの文章内で複数の記号を同時に使用する場合は、視覚的な整理や脚注番号との連携も意識して配置することが重要です。
Q: 順番に注釈を付けたいときは?
A: 通常はアスタリスク(*)から始めて、†(ダガー)、‡(ダブルダガー)、§(セクション記号)、‖(ダブルパイプ)などを順に使用する方法が一般的です。
さらに注釈が増える場合には、数字やアルファベットを併用することで対応できます。
ただし、あまりに多くの記号を並べると視認性が損なわれるため、脚注番号や注釈記号の選定には注意が必要です。
文書の構成が複雑になる場合は、注釈の順番に対応した一覧をページ末尾に添えるなどの工夫を加えると、読者の混乱を避けることができます。
アスタリスクと米印の選び方のポイント
- 読者層を意識する:ビジネス文書や公式文書では米印、カジュアルなWebコンテンツではアスタリスクが親しまれています。
- 文書のフォーマル度を考える:形式ばった文書には米印が適しており、柔らかい印象を与えたい場合はアスタリスクが効果的です。
- メディア(Web/印刷)に応じて最適化する:印刷物では米印の方が視認性が高く、Webでは文字化けの少ないアスタリスクの方が使いやすいことが多いです。
- 多言語環境を考慮する:国際的な文書にはアスタリスクを用いると違和感が少なく、情報が伝わりやすくなります。
補足:実際の使用時の注意点
記号が小さく見えにくい場合があるため、サイズやフォントの調整は非常に重要です。
特に印刷物やPDF資料では、解像度や拡大表示への対応を考慮し、記号がつぶれたり見落とされたりしないように設計しましょう。
また、読みやすさを第一に考え、注釈の数を絞ったり、必要に応じて文中に簡潔な説明を添えたりすることも効果的です。
記号の過剰な使用は読者の負担になるため、意味のある情報だけに限定し、文脈とのバランスをとりながら活用することが求められます。

